死の受容
厚生連高岡病院に勤務されていた内科医の狩野哲次先生をお招きして、終末期医療が抱える問題についてのお話を伺ったことがあります。その中で印象に残ったことがありました。
現在では、癌にかかると大抵の場合、患者さん本人に直接病名を告知されるそうです。治る見込みがある場合も、治る見通しの立たない場合も告げられる。進行した癌などは、医療技術が格段に進歩した現代にあっても、やはり治らないわけです。個人差はあるにしても、聞かれれば、だいだい余命は何か月ぐらいではないかということを告げられる。そうすると告げられた患者さん本人は、残された余命をどう生きたらいいのか、悶々と孤独に悩まれるということが多いということです。
生への執着や死への不安、恐れ、さまざまな思いが錯綜し、なかなか死を受容できない。
特に現代の日本人は、死んだらお終い、何も無くなるという意識が強くて、死に対するタブー、不安、恐れが、昔から比べると強くなってきていることもその要因の一つではないかと指摘されていました。
日常の生活で、終末期の迎え方、死というものをどのように受け止めたらいいのか、ほとんど考えようとされていない。家族で話し合うこともない。そういう状況の中で、だれか家族の一人が、癌などで終末期を迎えたらどうでしょうか。あなた死ぬ人、私残る人という後ろめたさもあり、死んだら終わりだという意識があるから、患者さんの気持ちを慮って、死に関する話題を避けようとする。患者さん本人も、しっかりとした死生観を持っていないと死と向き合うことを避けてしまう。1%の可能性に望みをかけて、最後まで治る希望を持って生きていかれる。周りも本人も「死」という問題をオブラートに包んで表に出さない。しかし、自分が死なねばならないという苦悩や不安が解消されたわけではありません。患者さん一人が孤独に心の中で悩まれるということだと思います。
死の迎え方
狩野先生は、以前終末期に関するアンケート調査をされたそうです。その中で、「あなたはどのような死を迎えたいですか」という設問に対する答えが、二つに大勢を占めた。一つは、何らかの形で自分の人生を総括して、自分の人生に満足して、周りに感謝しながら終わっていきたい。二つ目は、できるだけ周りに迷惑をかけずに、無駄な延命治療はせずに、ポックリと死にたいということです。
ポックリ死ねるかどうか、周りに迷惑をかけるかどうかは、その時の御縁次第でしょうが、それでも最後は、自分の人生に満足して、感謝して終わっていきたいというのが、私も含めた多くの方の心情だと思います。
しかし、死の受容がうまくできていないと、自分の人生に満足して、周りに感謝するどころではないという現実があるようです。幾つか事例を紹介してくださいました。
七十代後半の男性。煙草の害からくる慢性閉塞性肺疾患の患者さんですが、病状は治る見込みがない。ある日家族から、先生の口から言ってほしいと頼まれたこともあって、本人に病状を説明して、「治る見込みはありません。このままでは亡くなるかもしれない。息子さんに身代を譲るなど身の回りの整理や心の準備をされたらどうですか」と話した。そうしたら、「先生まだまだ早いでしょう」と言われた。こんな手遅れの酷い病状を説明しても、なお、自分の死と正面から向き合うことができない。それ以上何も言えなかった。
それから、七十代後半の女性。卵巣がんの末期で、抗がん剤治療で二年間延命をされた。最近は、抗がん剤治療も進んできて、延命する期間が長くなった。それだけ終末期を長く経験しなければならない。
そして、最後は抗がん剤も効かなくなって万策が尽き、沢山転移が見られるようになってきた。そういう状態になった時、患者さんに話したそうです。するとその患者さんは、「どうしてもだめなんですか。もう治療法はないんですか。それじゃこのまま何もしないで死ぬのを待つだけなんですか」ということを話された。その時先生は、この二年間の治療は何であったのだろうか。医療従事者としては、患者さん本人が、自分の人生を総括して、死への心構えをしてもらいたかったのだが、結局問題を二年間先延ばしにして、最初に戻っただけなのか、と思われたそうです。
それでも何か治療を続けてほしいいうことで、続けたが、吐き気や頭痛の副作用が激しくて治療を止めた。そうするとその患者さんはどうなったかというと、何を話しかけても、ただじっと上を見て、目を開けたまま一切応答しなくなった。うつ状態になって亡くなっていかれた。というお話でした。
家族も、医療従事者も、何とかしたいとは思っても、死の受け入れは、患者さん本人の心の問題です。やはり、元気な時から、自分の死をどう引き受けていくのかをトレ-ニングしないといけない。死の受容のために何が大事かというと自分なりのしっかりした死生観を持つことです。ところが、これは甚だ難しい。それだけに一生費やしたり、作れなかったりする人もいる。だからご縁のある宗教からそのことを学ぶということも大切なことではないでしょうか。特に富山県は、浄土真宗のご縁の深いところである。浄土真宗が、明らかにしてくださった仏教は、死んだら終わりという教えではありません。この世の生が終われば、新たに仏としてのいのちがスタートすると教えてくださっている。そういう教えにも耳を傾けながら、しっかりとした死生観を持つことが大切であると強調されていました。
死はタブーなのか
フランスの民族歴史学者フィリップ・アリエスは、「死をなじみ深く、身近で、和やかで、大して重要でないものとする昔の態度は、死がひどく恐ろしいもので、それをあえて口にすることも差し控えるようになっているわれわれの態度とは、あまりにも反対です。」と、西洋の「死」の歴史を振り返って、そう述べています。そして、このような変化は、西洋では二十世紀の中頃から、顕著になった。その理由をアリエスは、二十世紀に入って人々は、「人生とは幸せであることが大切であり、死の苦しみや醜さは、幸せの生活を混乱させるもので、出来るならばそれを見せないでおきたい」と考えるようになったからであると言う。そうした考えを起こさせる原因の一つが、人が病院で死ぬようになり、死が(醜いもののように)人の目から覆い隠されていったためであると言っています。
このような状況は、日本においても同じようなことが言えるのではないかと思います。
一昔前までは、暮らしの中の日常風景として生老病死がありました。死は、日常的なものであり、自然なものとして引き受けていくべきもの。また、死者と共に生きているという感覚もあり、今日ほどの死に対するタブーや恐れはなかったように思えます。つまり、死とうまく折り合いをつける文化や精神性を持っていた。
ところが、今日は、病気や老いや死は、人間を不幸のどん底に落とす敗北でしかないから、見ようとしない。そりより、若さや健康を追い求めることが、人間を幸福にするということがより意識されるようになってきたのではないか。老病死が、家という日常生活空間から病院や施設へと隔離され、身近に見えなくなってきたことも、そのことを助長してきたように思います。
その結果、不都合な病気や老いや死に対して、精神的に弱く、もろくなってきた。つまり、うまく死ねなくなったということではないでしょうか。
病気や老いや死は、避けて通ることのできない私の命の一部です。それを避けて都合の良いところだけを求めていくことが幸せだ、生きる意味だと思うことは、自分の生きる意味を非常に脆弱なものにします。今日の終末期(死の受容)の問題もそのことを物語っているように思えます。
自分の死から目をそらすことなく、仏法の中に、死を乗り越えていく道と本当の生きる意味を見出したいものです。
釈尊のさとり
釈尊の出家の動機の一端を物語る「四門出遊(しもんしゅつゆう)」というお話しがあります。
ある日、物思いに沈みがちであったシッダールタ王子(のちの釈尊)を心配した父の浄(じょう)飯(ぼん)王(のう)は、家来を連れてカピラ城の東の門から遊びに出されます。
その折に、道端を顔がしわまみれで、こしが曲がり背中をまるめ、杖にすがって喘(あえ)ぎながら歩いている人をご覧になりました。
「あれは、なんだ?」と家来に聞かれます。
「老人というものです」
「わたしもそうなるのであろうか」
「そうです。人間はみんなあんなすがたになるのです。シッダールタさま、あなたもです」
「わたしも、ああなるのか」
そう言われた王子は、青春の輝きも色うせ、意気消沈して城へと帰って来ました。
別の日、今度は南の門から遊びに出られます。
そこで、病人に出会われ、同じような質問をします。
「あれは?」
「病人です。人間は、いつかあのように病気になって苦しまねばなりません。王子あなたもです」
つらい気持ちになり、ふさぎこんで直ちに城に帰られました。
また別の日、西の門から遊びに出られます。
今度は、葬式に出会われました。
同じような質問をして、私も最後は死なねばならんのかと、いよいよ沈みこんで、城へと帰って行かれました。
次の日です。北の門から遊びに出られた時に、褐色の衣を身に着け、厳(おごそ)かに歩いて行く一人の修行者に出会われました。穏やかですがすがしい顔をしています。
そこで、王子は聞きました。
「この世は、楽しく生きたいと思っても、老病死という苦悩から免れることはできません。そう思うと気が沈み、悩まずにはおれません。なのに何故あなたは、そんなすがすがしい顔をしておられるのですか」
「あなたもね、修行をして真実(法)がわかるというとこんなような顔になりますよ」と修行者はこたえました。
このような出来事が、出家の動機になったのではないかというお話です。
さて、出家した釈尊は、当時の習慣にならって、先ず徹底した苦行に入ります。それは、苦しみや悩みに負けない強靭(きょうじん)な精神や肉体を鍛えるというものでした。しかし、体は骨と皮となり衰弱していくばかりです。
やがてそのことの無意味さに気付いた釈尊は、スジャータの乳(ちち)粥(がゆ)の施しを受け、元気を取り戻して菩提樹の下で瞑想に入ります。
釈尊の瞑想の課題は、何であったか。おそらくは、こういったことではなかったのでしょうか。
「なぜ自分は苦悩するのか。苦悩の原因は何か。鳥や牛というような動物は、人間と同じように、年をとり、病気になり、死んでいくのに、そのことを悩んでいるようには見えない。ありのままに与えられた現実を生きている。なぜ人間である私だけ
が、老病死の現実に悩むのか。」
瞑想の中から、釈尊がさとり気付いたのは、私が悩むのは、悩まそうとするはたらき(法)がはたらいているからだ、という発見でした。
そのはたらきを「阿弥陀(あみだ)」と教えてくださいました。「ア」は否定語で、「ミダ」は量(はかり)という意味で、一メーター、二メーターという物差しです。つまり、私の自分中心的な我に執着するという我執の物差しでない、真実(法)のものさしがはたらいているということです。
よく釈尊のさとりを万有引力の法則を発見したニュートンにたとえられることがあります。ニュートンは、リンゴが木から落ちるのを見て、その法則を発見しました。釈尊は、苦悩する自分の事実から、阿弥陀の法のはたらきを発見しました。その法のはたらきに耳を傾け従っていくところに、自分のものの見方考え方が正され、苦悩から解放されていく道があるとお説きくださいました。
私たちの日常を考えるとどうでしょう。
幸せと思う時や楽しい時には自分の人生が問題となるようなことはほとんどありません。何かに挫折し、老病死の事実に苦しみ悩む時、自分の人生は何であったのかと問われ、私のあり方が課題となってきます。そこに仏法を聞こうという心も開かれてきます。
以前岡西法英という先生が、「神経の願い」という話をされていたことを思い出します。
私たちはあまり意識したことはありませんが、体の中には神経というものが流れている。怪我をしたり、胃などを無理すると痛いと感じます。「ああ、私の体には神経が流れていた」とそこで意識するわけです。私たちは、ある意味で健康であってくれという神経の願いの中に生かされているといってもいいのではないか。その願いに反すると痛いという形で、私にその願いを届けてくれる。それに気づいて、病院へ行ったり摂生(せっせい)していくと自ずと健康を回復していくが、好き勝手にやっていると健康を害していく。
というような話でした。
これと同じようなことではなかろうかと思います。
私の苦悩を通して、阿弥陀の願いが届けられているということです。
また、ヴァッカリーという釈尊の弟子の話も示唆にとんでいます。臨終の間際にもう一度釈尊を礼拝したいという願いに応じて、釈尊が枕元にやってきます。一心に釈尊を拝むヴッカリーに対して、
「私もやがて朽(く)ち果てていく。私のこの汚れたからだをみて、何になるのか、私のこの体をみるものが仏を見るものではなくて、法を見る者こそ仏を見るのだ」
と釈尊が発見した法に従って生きることの大切さを教えてくださっています。
この法は、南無阿弥陀仏という名前(名号)となって私に届けられています。
その名号を称えながら、そこに込められた阿弥陀の法に従って生き抜かれた方が、親鸞さまでありました。
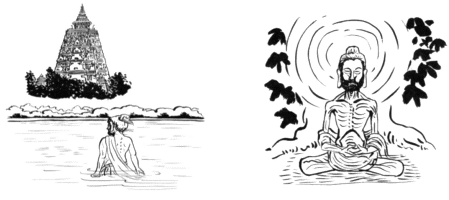 |
苦悩からの解放
お釈迦さま(釋尊)は「人生は苦なり」と教えてくださいました。自分の思い通りにならないと「苦」を感じますから、言葉を換えれば、「苦なり」とは、人生は「自分の思い通りにはならない」ということを言われているのではないかと思います。
私でしたら、寺に生まれようと思ったのでもないのに、生まれてみたら、寺の息子であった。「生」は自分では選べません。それではと、せっかく人間として生まれたのだから、いつまでも若くて健康で長生きがしたい。そう思っても、自分の思いとは関係なく、やがて年を取り病気になって、死にたくもないのに死んでいかなくてはなりません。人間として生まれたということは、人生は自分の思い通りにはならないという、根本的な苦悩を背負って生きていかねばならないということです。
確かに、人生には楽しい時や幸福を感じる時もあります。しかし、その時においても根本的な苦悩は解決されたとは言えず、ただ忘れているだけかもしれません。また、「諸行無常」は厳然とした真実ですから、楽しさや幸福は必ず壊れていくようになっています。今あるものが無くなっていく、そこに不安や苦悩を感じるのも事実です。大無量寿経には『田あれば田に憂へ、宅あれば宅に憂ふ。〈中略〉田なければ、また憂へて田あらんことを欲(おも)ふ。宅なければまた憂へて宅あらんことを欲(おも)ふ』と、田や家が有れば、どうやって維持しよう、無くしては大変だと憂い悩む。また、田や家が無ければ、何とかしてほしいと憂い悩む。有っても無くても苦悩する、私たちの生活のあり様を言い当ててくださっています。
実は、私たちは楽しい時も幸福を感じる時も、根本的な苦悩の構造からは、解放されていないということになるではないでしょうか。
それでは、なぜ苦悩から解放されないのか。
釋尊は、その原因は自己中心的な執(とら)われ、自分にとって都合の良いものに執着する心(煩悩)だと見抜いてくださいました。「諸行無常」ということは、永遠に変わらない常住の実体というものはない。あらゆるものは生滅変化を繰り返すという不変の真実です。いつまでも変わらない私というものはありません。ですが、私たちは「若くて、健康で、長生きする」ことが、素晴らしいことで幸せなことだという自分に都合の良いあり方に、執われてしか生きることができません。私の願いや夢も、殆んど「我執」(煩悩)の上に成り立っているのではないかでしょうか。
そうすると、私の与えられた命の事実は、「年を取り、病気になって、死んでいく」という私の思いとは全く逆の現実です。私の願いや生きる意味が、我執(煩悩)から出ている限り、命の現実によって必ず裏切られることになります。苦しみや空しさから逃れることはできません。
釈尊は、そういう私たちに、苦悩の原因を明らかにしてそれから解放される、さとりと安らぎに至る道を明らかにしてくださいました。
さて、釈尊滅後です。在家信者にとって、釈尊の教えは、理屈としては理解できても、出家して僧侶となり実践することは不可能に近いことでした。煩悩の執われから逃れられない私たちにさとりに到る道などあるのか。どのように生きればよいというのか。
いや、在家信者のまま、救われていく道、さとりに到る道があることを説かれていかれたはずである。そこにこそ釈尊成仏の目的があったのではなかろうか。
そういう圧倒的多数の在家信者の、仏道を求めていこうという歩みの中から、釈尊が残された教えの再構築がはじまり、大乗仏教は生まれてきたのではないかと思います。
その生き方のモデルになったのはやはり釋尊でした。この世で我執(煩悩)から解放されさとりを開かれたのは、歴史上ただ一人釋尊です。その釈尊は、さとりをひらいた後、どのように生きられたのか。
それは、自分のために生きられたのではありません。生涯を通じて悩める人を救い続けて、他者のために生きられた人生でした。つまり、悟りをひらくという「自利」(智慧)は、同時に他者を救い、他者のために生きるという「利他」(慈悲)と一つではないのか。むしろ、他者のために生きるということは、自らさとりをひらくということの中味である。
釈尊の生きざまから再確認された大乗仏教のさとりの境地は、自利利他の完成、他者のために慈悲利他に生きるということでした。
また、釋尊滅後在家信者を中心に、釈尊の前生の物語(ジャータカ物語)がつくられていきます。釈尊在世当時は、すでに輪廻転生、因果応報という考えは社会に浸透していました。この思想は、身分差別であるカースト制度を支えていて、釈尊はそれからの解放を説かれたのでした。ですから、僧侶集団が積極的に関わったとは考えづらく、おそらく在家集団中心の作業ではなかったかと思われます。
この世でさとりを開かれた釈尊は、さぞかし前世で善行を積み重ねて来られたに違いない。
そういう善因の積み重ねが、この世でさとりという楽果を生んだのであると。
現存するパーリ仏典には、五四七の前世物語(ジャータカ物語)が残されています。それによると、釈尊は九一劫年前、スメーダという苦行者でありました。ある時、ディーパンカラという仏(燃(ねん)灯仏(とうぶつ))に出遇い深く感動して、「世の人々を救う仏とならう」と誓願を起こし、菩薩としての修行をはじめます。菩薩(ぼさつ)とは、菩提薩埵(ぼだいさつた)の略語です。他者の救済を願い、自利利他の完成であるさとり(菩提(ぼだい))を求めて修行する人々(薩埵(さつた))という意味です。釈尊のさとりを求めて歩む前世の姿が菩薩と表現されました。
このスメーダ青年の姿を見たディーパンカラ仏は、「汝は遥(はる)か未来に釈迦如来という仏となる。そのため九一劫という年月、五百十数回生まれ変わって菩薩の修行をせねばならぬ」と、必ず仏になるという保証の予言である「授記(じゅき)」というものを授けられます。その授記(じゅき)の通りスメーダは五五〇回生まれ変わり、菩薩の善行を積んで、今世において釈迦如来という仏となったと説かれています。
その菩薩行を書かれたジャータカ物語には、時には動物に生まれ変わ
り、他者の救済のために、慈悲行や布施行を実践していく。他者のために自らの命を捨てていく「捨身(しゃしん)」の話が、綿々と語られています。
他者のために生きるという菩薩行の繰り返しの中に釈尊のさとりの完成があり、その生き様は、必ず仏になる道であるとディーパンカラ仏は授記を与えているのです。
このように釈尊前世物語の作成や、更には釋尊を讃歎する作業も同時に進められていきます。最終的には、釈尊とその教えの永遠性と普遍性を讃歎することが最高のものとなります。釈尊こそ「無量寿・無量光」であるというのです。大乗仏教には沢山の諸仏(諸々の仏方)が登場してきますが、釈尊のさとりも諸仏のさとりも同じはずですから、釈尊も含めて諸仏は皆「無量寿・無量光」になります。この無量寿(アミターユス)・無量光(アミターバ)が合わさった言葉が阿弥陀です。諸仏に共通する「「無量寿・無量光」を自らの名乗りとして阿弥陀如来は登場してきたのでした。そこに大乗仏教が凝縮され、集約された精神があるように思えます。
大乗仏教は、自我の執らわれに気づきながら、自他は一如(いちにょ)であるという阿弥陀に集約されるような「智慧」のうながしを受け続けていく。そして、他者のために生きようとする「慈悲」のところに、さとりへの道は必ず開かれていくことを教えているように思います。
苦悩から解放されるということは、どんな苦悩もいとわない何ものか、精神を見出すことです。大乗仏教は、そのことを指示(さししめ)してくれています。
幸せということ
一頃、ブータンが「幸福の国」ということで話題になったことがあります。2005年の調査では、国民の実に97%が「幸せである」と答えたということです。2011年には、ブータン国王夫妻が来日されています。その折、ブータンの政策として、国民総生産(GNP)よりも国民総幸福量(GNH)を重視している。つまり、経済発展(物質的豊かさ)よりも、「国民の幸福」(精神的豊かさ)の実現を目指していることが紹介されました。そして、そのことの大切さを世界にも提唱されているということで、さらに大きな波紋を生みました。
現に、国連を動かしています。
2012年、国連が3月20日を「国際幸福デー」とすることを採択し、国民の幸福の実現をめざす施策の大切さを確認する日としました。以来、毎年(2014年は発表なし)世界の幸福度ランキングを発表するようになりました。
因みに、2018年の発表は、世界156カ国中、1位はフィンランド、2位はノルウェー、3位はデンマークです。調査の項目には、経済だけではなく、自由と平等、平均寿命や福祉、政治の腐敗などが含まれています。社会保障や福祉などがしっかりしているということなのでしょうか。毎回北欧が上位を占めています。18位アメリカ、54位日本、57位韓国、86位中国、97位ブータン、150位シリア、156位ブルンジなどとなっています。
国際的な幸福を測る調査項目の尺度からすると、ブータンはかなり下位の方です。それなのに、なぜブータンの国民はそんなに幸福だと思っているのでしょうか。誠に不思議です。
ブータンの国教は仏教でして、国民一人ひとりに仏教の精神が根付いていると聞いています。そのことと何か関係があるのではないだろうか。当時、いろいろ調べてみて、二つの事に思い当りました。
一つは、「常に周りの人の幸せを願う」ということです。熱心な仏教徒であるブータンの人々は、毎日何十回と仏様に手を合わせます。日本でしたら、自分や家族の病気回復や合格祈願など、自分たちのことをお願いすることが多いような気もします。ところが、ブータンの人たちは、周りの困っている人がたすかり、幸せになれるようにとお祈りするんだそうです。
仏教が私たちにもたらしてくれる「いのちへの目覚め」は、私は一人では生きていない、生きられないということです。気がつかないほどの多くの人やモノとのつながりや関係性、支え合いのなかで成り立っています。幸せも一人では成り立ちません。人との出会いや孫に恵まれるなど、そのつながりのなかで感じていくものです。人はつながりや関係性のなかで存在しています。ですから、つながっている周りの人が幸せにならなければ、自分も幸せになれません。
そして、周りとの関係性やつながりに気づいていくと、自然と感謝の気持ちがわいてくる。そうすると自己中心的欲望からも解放されて、「足ることを知る」ということが身についていきます。
二つ目は、仏教の生き方である「小欲知足」(欲を少なくして足るを知る)が身についているということです。資本主義の中に生きていますと生まれながらにもっている自己中心的な欲望を満たすことが、幸せだ喜びだと振り回されそうになります。ですが、周りから支えられ生かされている命の事実に気づくと、現在の状態に満足する心が開かれてくるということなのでしょう。
この二つの点からも、ブータンの人たちには、仏教の精神が確かに息づいている。そして、そのことが幸せと感じさせるもとになっているのではないかという思いが致しました。
日本ではどうなのか
それでは、日本ではどうなのでしょうか。戦後たびたび、都道府県別生活満足度調査が行われてきました。いつも1位の県がありまして、福井県です。2011年の法政大学の調査では、1位福井県、2位富山県、3位石川県です。2018年の日本総合研究所の調査では、1位福井県、2位東京都、3位長野県、4位石川県、5位富山県になっています。今までの調査を見てみると大抵北陸3県が上位を占めています。
これは以前紹介した話ですが、二十数年前、このことに福井新聞が疑問を持ちました。どうしてうちの福井県民は、経済的にはとても一番とは思えないのに、日本で一番幸せだと思っている人が多いのだろうか。
そういえば、福井県は寺院の半数以上は、浄土真宗の寺院である。浄土真宗の教団隆盛の礎を築いた蓮如上人の越前吉崎の御坊もあった。浄土真宗の信仰に生きる人が、他と比べて圧倒的に多い。このことと何か関係があるのではないか。一度調べてもらおう。
そこで、当時大阪市立大学の文学部部長であった金児暁嗣教授に依頼をしました。先生は、現地調査や大阪、福井県の大学生の意識調査などを通して結果を公表されています。
その概要を読んだ時、印象残ったのは大阪の学生に対して福井県の学生の方が「おかげさま意識」が高かったこと。それから「感情のバランス」の調査をおこなったとき、大阪の学生は何となくイライラしている。それに対して福井県の学生は感情のバランスがうまくとれているということです。大阪の大学生というのは、全国から来られていますので、ある意味全国平均ということかもしれません。それに対して、福井県の大学生は地元の方が多く、その分地元の意識を色濃く反映しているものと思います。
また、「おかげさま意識」が高まると幸福感も高まると指摘してくださっています。
現状に不平不満があるとイライラしてきます。それは私の心が決めることです。ところが私は一人では存在していなかった。先祖をはじめいろんな方々の支えやはたらきのなかで、生かされ支えられているいのちであったと気づかされてくると、感謝する心や御恩を感じる心がわいてきます。そうすると「おかげさま意識」が高まってきます。「おかげさま意識」が高まってくると、心がほっこりし、幸せを感じる心も高まるということではないでしょうか。
北陸3県は、なぜ生活満足度が高いのでしょうか。
それは多分に「おかげさま意識」ということと関係しているように思います。北陸3県は、浄土真宗の寺院の占める割合が、5割6割と多数を占めています。確かに浄土真宗の教えは、生かされているいのちへの目覚めを促すものです。しかし、それにも増して、北陸三県の先人たちは、他府県に比べても厳格に先祖の追悼儀礼を行ってきたように思います。五十回忌までねんごろに年忌法要を勤め、そこに集えるお互いのつながりの中から生きる幸せを感じ取ってきました。毎月僧侶に月参りをしてもらう。お盆には墓参り。更には、ご縁のあるお寺で先祖方の永代経法要を営み、年に一度は各家庭でも寺院でも報恩講を勤めてきました。
先祖の追悼儀礼を積み重ねていくと「おかげさま意識」は深まっていきます。
先人が、そうやって何百年間にもわたって、厳格に先祖の追悼儀礼を営んできて下ったうえに「おかげさま意識」の高まりがあり、北陸3県が常に上位を占める要因の一つになっているのではないかと私には思えました。
先人は、先祖への追悼儀礼を通して私たちに何を伝えようとしてくださったのでしょうか。その先人の思いを汲み取りながら、今年も西照寺にご縁のある全門信徒の祠堂永代経法要をお勤めしたいと思います。
報恩講とは、どんな行事なのか
報恩講(ほうおんこう)とは、宗祖(しゅうそ)親鸞(しんらん)聖人(しょうにん)の御命日をご縁にお勤めする法座です。
親鸞聖人は、一二六三年一月十六日(弘)長二年十一月二十八日)、九十歳にてご往生されています。この一月十六日(旧暦では十一月二十八日)が祥月命日にあたります。
聖人の亡くなられた日に、その恩徳を偲びお勤めをし、仏法に自らの生き方を学び直そうと集いがもたれました。この集いを「講(こう)」といいます。もともとは、親鸞聖人自身が、師の法然上人の御命日に、集いをもったことに由来があるようです。
一二九四(永仁二)年には、聖人の曾孫にあたる本願寺第三代の覚如上人が親鸞聖人の三十三回忌に際し、「報恩講)私記」を著しそのお徳を讃えられています。このことから、その集いを報恩講というようになりました。当初は、毎月の命日にお勤めされていたようですが、本願寺第八代蓮如上人の頃から、年に一度祥月命日に合わせて七日間(七(しっ)中夜(ちゅうや))お勤めをする形式になったようです。これを「御正忌(ごしょうき)報恩講(ほうおんこう)」といいます。
この本山で勤まる御正忌報恩講に全国の門信徒がこぞってお参りできるようにと、前もって、各末寺や各ご門徒の家庭でも報恩講が営まれました。それでも、なかなか本山にお参りできないということで、各末寺でも御正忌報恩講が勤められるようになりました。
ですから、報恩講とは、直接的には親鸞聖人の「ご恩に報いる集い」ということになります。聖人の生き方を通して、私自身の生き方を確かめ見直す大切な日です。
先人は、この浄土真宗教団の根幹をなす最も重要な報恩講の仏事を、七百年を超える長い歴史を通して、脈々と受け継ぎ今日まで大切にお勤めしてくださいました。
親鸞聖人の御恩とは何か
それは私の「いのち」の真実を 明らかにし、阿弥陀如来の願いと 明らかにし、阿弥陀如来の願いと
救いに、私の生きる意味と死を乗
り超えていく方向を指し示してく
ださったことにあります。
そもそも釈尊は何に目覚めたの
でしょうか。
雑阿含(ぞうあごん)経(きょう)巻十二には『この縁起の法・道理は、その法を覚証(かくしょう)する如来(にょらい)(仏)が世に出ても出なくとも常住(じょうじゅう)であり法(ほう)住(じゅう)(まこととして定まっているもの)』であると書かれています。私の与えられている命の事実を「縁起(えんぎ)」という言葉で、表現してくださいまして、それが真実であると言われます。縁起とは、因縁によって生起しているという言葉の略語です。一切の存在は、あらゆるものが相互に依存し関係し合い、つながっている。それらが、無数の原因と条件によって(因縁)、仮に依り集まってものを成り立たせている(生起)。そして、時がたてば、条件が変われば違うかたちになっていく。永遠不滅のようなものは存在しない。常に消滅変化を繰り返しているということです。
言い方を変えると命というのは自分のものではなくて、(自分以外の)いろんなものが仮に寄り集まって成り立っている。自分のものではありませんから、自分の思うたようにはならないということです。
ところが私は、与えられている命を自分のものだ、自分の命だとしか思えていません。
今、私の命を「生・老・病・死」と表現しますと、これは私の一生です。その中で「生」に対して「死」、「老い」に対して「若い」、「病気」に対して「健康」を分けてみます。本来の命の事実からすると、生も老も病も死も、どれが良いとか悪いとかなく、共にどの状態であろうと百点満点の命を生きています。 しかし、私は「若い」とか「健康」とか「長生き」することが、幸せだ喜びだと思って、それを求めて日暮らしを送っています。「老い」や「病気」や「死」は、マイナス点であり、不幸のどん底のようにしか見れませんから、そこに苦しみや悩みを感じる私がいます。
釈尊は、与えられている命を自分の都合の良いようにしたいという「我執(がしゅう)」の見方こそが問題であり、苦しみの元であると気づいてくださいました。
雑阿含経七五三経には、(比丘)『尊師よ、不死(、不死と言われますが、尊師よ、何が不死なのですか。何が不死に至る道なのですか』。(仏陀)『比丘よ、およそ貪欲(むさぼりの煩悩)の滅尽、瞋恚(いかりの煩悩)の滅尽、これが不死と言われる。この聖道こそが不死(涅槃)に至る道である』と書かれています。与えられている縁起なる命を自分の我執煩悩でしか見れない。その我執煩悩の見方から解放され(縁起そのままに生きれる)ことが、死を乗り超えていく道(不死)であり涅槃に至る道であると言われます。
ですから、仏法を聞かせていただくということは、一義的には、病気が治ったり、若くなったり、長生きをするということではありません。それが素晴らしいことで幸せだという見方(我執煩悩)から、解放されることによって苦悩から救われるということなのです。
縁起がかたちを現す
縁起ということは、生きとし生けるものは、どこかでつながり関係し、支え合っているということへの目覚めを促(うなが)します。
親鸞聖人の言葉でいえば、『一切の有情はみなもって世々生々の父母・兄弟なり』(歎異抄)第五章)ということです。命のあるものはすべてみんな、これまで何度となく生まれ変わり死に変わりしてきた中で、父母であり兄弟・姉妹であったという、つながりや関係への気づきです。
私でも、知らないところ所へ行って全然関係のない人と思っていた人が、私と関係する人だと分かると急に親しみを覚えたり、困っていることがあれば親身に何かしてあげたいという思いに駆られることがあります。
縁起の法に目覚めた釈尊は、すべてが親兄弟のようにつながっているというその奥底に、我がことのように困っている者を助けたい。
迷っている者を目覚めさせ救いたいという、はたらきを感得されたように思います。そのはたらきが、私たちに分かるように、かたちとなって、人格的表現なって現れた方が阿弥陀様であると親鸞聖人は教えてくださいました。
ですから、阿弥陀様という方が西方浄土におられて、私を救って下されるといういただき方も大切でありますが、それは同時に、私の命の事実に宿っているはたらきを阿弥陀と名付けたという言い方もできるかと思います。
阿弥陀様はすべてのものを救いたいと願われています。このすべてのものを救いたいという願いは、私の命の事実である縁起そのものの願いであるともいえます。
そして、その願いを念仏に込めて、これは本当はあなたの願いではなかったのですかと、私に届け呼びかけてくださっています。
親鸞聖人は阿弥陀如来の願いの中に、私の生きる意味と方向を指し示してくださったのでした。
  
|
|
|