お経について
スートラ 
お経とは、お釈迦さまのお説きになった教えを文字にしたためたものです。サンスクリットの原語では、スートラといい、「糸やひも」という意味があるようです。
お釈迦さまは、多くの教えを説かれましたが、直接文字に書かれるということはありませんで、教えはお弟子たちなどによって口伝えに広まっていきました。お釈迦さまが、ご存命中はそれでもよかったのですが、お亡くなり涅槃(ねはん)に帰られた時に、これは大変だということになりました。人の記憶にたよる口伝では、教えが歪(ゆが)んだり、ぼやけていく危険があるからです。
そこで、「結集(けつじゅう)」というお弟子たちの集会を何回も開いて、教えを確認する作業がなされました。そして、これはお釈迦さまの説かれた教えに間違いないとお弟子たちが確認したものを、その当時でしたら、木の葉っぱみたいなようなものになのでしょうか、文字を書き記(しる)した。ある程度、重ね合わせて束(たば)になると「ひも」で綴(と)じてひとつの塊(かたまり)にして保存しました。
のちに、この経典の書かれていたものを束ね綴じていた「ひも」(スートラ)をもって、お釈迦さまの教え全体を象徴的に表現するようになったのではないかと思われます。つまり、お釈迦さまの教えとは何か、それはスートラだということです。
三蔵法師(さんぞうほうし)
下(くだ)って西暦三~四世紀ごろからでしょうか。中国では、多くの三蔵法師と云われる方々が、インドを訪れ経典を持ち帰り、国家事業として翻訳作業に取り掛かります。大抵の方は、西域のシルクロード(絹の道)を通ってインドに行かれていますが、シルクロードは別名「骨(こつ)道(どう)」とも言われています。道なき厳しい砂漠地帯を進んでいくわけですから、道に迷い、途中で倒れていく人もいる。砂漠の中に骨を残していくわけです。後から来た人は、その骨を目印にして、それを乗り越えて新たな道を開いていくということで、道を築いていく。それで骨道と言われているんだそうです。
初期の方に法顕(ほっけん)という三蔵法師がおられますが、この方は、十六年の歳月をかけて、インドから経典を持ち帰っておられます。骨道を通ってインドに着くまでに六年、現地で経典を学び収集するのに六~七年、帰りは海路に三年かかったようでして、大変なご苦労をされています。三蔵法師の中でも一番有名なのは、玄奘(げんじょう)三蔵(さんぞう)でして、その旅行記「大唐(だいとう)西域記(さいいきき)」をもとに「西遊記」が作られ、今日でも映画やテレビ等で孫悟空の話として上映されています。
因(ちな)みに、三蔵とは、お釈迦さまの教えを書いた「経蔵(きょうぞう)」と、教えに依った生活規範や戒律を記した「律蔵(りつぞう)」、それにお経を研究解説した「論蔵(ろんぞう)」という三つの宝(蔵)という意味でして、それを求めてインドに渡った訳(やっ)経(きょう)僧(そう)を三蔵法師といっているわけです。
そのように命を途中で砂漠の中に落とすという場合も多かったであろう、三蔵法師のご苦労によって、三蔵を中国へ持ち帰って、漢字に翻訳しました。この翻訳に当たって、中国の人は、意味をとって訳すというやり方と原語の発音を残すために、似通った発音の漢字に当てはめる音(おん)写(しゃ)という二通りの方法をとっています。
例えば、南無阿弥陀仏という言葉は、サンスクリット原語[namas(namo)〈ナモ〉、 〈アミダ〉、buddha 〈ブツ〉]の音写です。
音を写しただけですから、南が無い(南無)、どんな意味だろうと漢字を探ってみても全く意味はありません。意味は、「帰命」になります。南無阿弥陀仏とは、限りない「ひかり」と「いのち」〈阿弥陀〉の世界に目覚め、我々を救うためにはたらいておられる方〈仏〉に帰命〈南無〉、帰依するという意味になるのでしょうか。
経という漢字の意味
このようなことで、仏教全体を象徴的に表すスートラという原語は、経(タテ糸という意味)という漢字に翻訳されました。また、音だけとって、「修(しゅ)多羅(たら)」と音写されています。
ご存知のように、漢字は、ものの形をかたどった象形文字が多いんです。経という漢字も、織機(おりき)に縦糸をまっすぐ張り通したさま【持〈ケイ〉】を描いたところから象形されているそうです。また、経という字は、人間が、はたおり機の前に座って織物を作っている姿からきたのではないかと説明される先生もおられました。ですから、「糸」が人間で、「圣」は、はたおり機ということになるのでしょうか。
この縦糸を意味するところから、物事の根本精神とか、時代を貫くものというようなことを表す漢字として使われてきました。それをスートラの訳に当てたわけです。
また、これは以前聞いた話ですが、はたおりで一番神経を使うのは、縦糸を真っ直ぐ平行に引くことだそうです。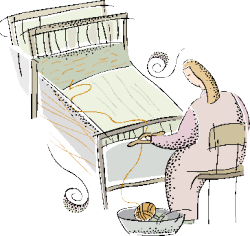 うまく引けたら、横糸の方は適当にやっていれは、りっぱな織物ができる。織物を作るに当たっては、縦糸の引き方が大切だということです。 うまく引けたら、横糸の方は適当にやっていれは、りっぱな織物ができる。織物を作るに当たっては、縦糸の引き方が大切だということです。
私たちの人生も同じようなことが思われます。お互い二度とない人生を人間として生まれてきましたが、それじゃ、自分の人生を通して、何を願い、どういう世界を築こうとしているのか、あなたの人生の縦糸はしっかり引けてますか。そう問われると何か心もとないものを感じます。煩悩に振り回され、美味しいものを食べたとか、どこかへ旅行に行ったとか、横糸ばかりに気をとられて、大切な人生の縦糸を見失いがちであります。
そういう私たちに、本当は人生の縦糸が大事なんですよ。そのことを教えてくれているのが、釈尊の教えであるから、早く仏法を聞くあなたになってください。
そういう訳経僧の、経という漢字に託した願いを感じますし、改めてすごい訳だなあと思います。
修多羅(しゅたら)という音写(おんしゃ)
それから、スートラの発音を残すために、修多羅と音写したといいましたが、この修多羅という言葉は、経典にも度々出てきますし、正信偈にも「依(え)修(しゅ)多羅(たら)顕(けん)真実(しんじつ)」(修多羅によりて真実を顕(あらわ)す)と書かれています。
そのほかに、僧侶が葬儀などで着る七条(しちじょう)袈裟(げさ)の飾りに用いる組紐(くみひも)にも修多羅という名前が付けられています。簡略に言うと七条という衣は、布切れを縫い合わせ、大きな長方形の布地にしたもの
を体に巻いて、左肩のところで紐(ひも)によって縛っています。後ろから見ると左肩から、その一本の大きな組紐が垂(た)れていますが、それを修多羅といいます。体に巻いた布地が横糸に当たれば、修多羅紐は縦糸に当た
ります。肩で縛っている修多羅が散(ばら)けると七条袈裟はバタッと下に落ちてしまいます。
皆さんは葬儀に亡き人を偲んで、葬場に来られますが、そこには七条を着た僧侶が読経をしていて、肩から垂れた修多羅が見えるはずです。亡き人を悲しんで来られたあなたも死なねばなりません。死を貫いていけるような、あなたの人生の縦糸はしっかりと引けていますか。縦糸(修多羅)がしっかりしていないと七条は散(ばら)けてしまうんです。どうか縦糸を教えている仏法を聞くあなたになってください。そういう願いが衣ひとつにも込められているような気がいたします。
七条を小さくしたのが、五条です。これも横糸にあたる長方形の布地を体に巻いて、縦糸にあたる「威儀(いぎ)」と呼ばれる肩ひもで結ばれています。威儀が散(ばら)けると五条は落ちてしまいます。これも七条と同じようなことを私たちに訴えているのでしょう。五条を簡略にしたものが、日常の法衣にかけている輪(わ)袈裟(げさ)になります。
葬儀や法事などで、お経を上げたり、聞かれたりする時には、お経という漢字にも、衣にも意味と願いが込められていることを感じ取っていただければ幸いです。

お布施
請求書と領収書
小学校四年生のケンちゃんは、お母さんに毎月三百円の小遣いをもらっていました。ところが、いつも直ぐに無くなってしまいます。お小遣いを上げてほしい。でも、お母さんはきっとダメと言うだろう。そこで、思い悩んだケンちゃんは、ある日お母さんに請求書をだすことにしました。
「この前、八百屋さんにお使いに行ったの五十円、食事の後片付け手伝ったの三十円、フトンの上げ下ろしをしたのが二十円、……………。合計三百円ください」
ケンちゃんは思いつくままにいろいろ考えて、お母さんに請求書をだしました。
すると、それを見ながらニコッと微笑んでいたお母さんは、次の日に
「この前、ケンちゃんが風をひいて熱をだして寝込んだときに、寝ずに看病したのが〇円、洋服のボタンがとれて困っていたのを縫ってあげたのが〇円、いつも食事を作ってあげているのが〇円、……………。合計〇円。お母さんはケンちゃんが仏さまの教えをよく聞いて、いつも優しく、素直な子に育ってくれるように願っています」
今度は、お母さんの方からケンちゃんに請求書がきました。
その時、ケンちゃんはハッと気がつきました。
一体何に気がついたのでしょうか。
そんな話を時折、お寺の子供会で話すことがあります。
以前でしたか、「おっちゃん、その話小学校の教科書に載っている」と言ってくれた子がいました。よく聞いてみると小学校の副読本に同じような話が載っているそうで、全国的にもよく知られた話のようです。
さて、ケンちゃんは一体何に気がついたのでしょうか。
それは、ケンちゃんが請求書をだす前に、お母さんからたくさんな愛情やはたらきをいただいていた。つまり、請求書に対すれば、お母さんからいっぱい領収書をいただいていたということだろうと思います。
私たちは、自分の思いが叶えられたならばと、お金が儲かりますように、立派な家が建つように、子供がこの学校に入学できれば、あの人がもっと心がけてくれれば、………とまわりに請求書を乱発しています。そして、それが満たされたなら、幸せだ、安心だ、満足だという日暮らしをおくっています。
しかし、自分の命というものを仏さまの教えから照らしだされると、全く一方的に与えられた世界に成り立っていた命だったと気づかされます。頼んだわけでもないのに両親や家族からたくさん領収書をもらっていた。目に見え
ないいろんな働きや大自然の恵み、もっと深くには、私の生死を貫いて働いてくださっている阿弥陀の働きがありました。
北原白秋は、
「薔薇(ばら)ノ木ニ 薔薇ノ花咲ク ナニゴトノ不思議ナケレド。薔薇ノ花 ナニゴトノ不思議ナケレド 照リ極(きわ)マレバ木ヨリコボルル 光リコボルル」
と薔薇一輪の中に、大自然の私へのはたらきを、領収書をいただいていたことを、感動を込めてうたっています。
改めて、私たちは請求書をだしてしか生きられないのかもしれませんが、それ以前にたくさんの領収書をいただいていることへの気づきの大切さを教えられます。
お母さんからの領収書に気がついたケンちゃんはどうだったのでしょうか。やはりうれしかったんじゃないでしょうか。しあわせを感じたに違いありません。
御布施(おふせ)のこころで
仏教では、さとりの世界を彼岸(ひがん)といいます。それに対して、この世は、迷いの此(し)岸(がん)になります。
迷いの此岸から、煩悩の川や海を渡ってさとりの彼岸に至る。そのために六波羅蜜(ろくはらみつ)という六つの実践徳目があると説かれています。六つとは、布施、持戒、忍辱(にんにく)、精進、禅定、智慧のことです。波(は)羅(ら)蜜(みつ)とは、到(とう)彼岸(ひがん)と訳され、彼岸(さとり)に到る行と説明されています。
この六つの行の最初にでてくるのが布施であり、仏道を歩もうとするものにとって最初の入り口となるべき、大切
な徳目ということになります。意味は、漢字の通り、あまねく(布)ほどこす(施)、他に与えることです。あまねくですから、わけへだてなく誰にでも平等にということです。別な言い方をすると、自分への執着を捨てるということ
です。
私たちは、自分の執着が満たされることが、請求書が満たされることが、幸せだと日暮らしを送っています。しかし、自分への執着を捨て、私の命の立脚地がそうであるような、領収書の精神に立ち返っていくことが、仏さまの
こころに近づく大切な最初の一歩である。そしてそう気づくことが、本当の幸せなんだということを仏教は教えてくれているように思います。
この布施には、財物を施す財施(ざいせ)、法を説く法施(ほうせ)、無畏(むい)(おそれなき心)を施す無畏施(むいせ)の三つがあると説かれています。
門信徒の皆さんとお寺やお坊さんは、門信徒の皆さんからは財施を、それに対して、お寺やお坊さんからは法施(読経や法を伝えていくこと)をという布施の関係で成り成っています。読経に対する料金を「御布施」というので
はありません。料金価格があるのならば、それは請求書の世界ですし、商売の関係になってしまいます。
世の中に、布施の精神で成り立っているお寺やお坊さんがいるということは、人間にとって何が大切なのかを形や身をもって伝えていこうとしている一面もあるように思います。
ローソクと花とお香
浄土真宗では、仏壇にお参りするときも、お墓にお参りするときもローソクと花とお香(線香)は欠かせないものになっています。それでは、これらにはどのような意味と願いが込められているのでしょうか。
このことを改めて明らかにしてくださった方に花山(はなやま)信(しん)勝(しょう)という和上(わじょう)さんがおられました。この和上は、戦後東京の巣鴨の刑務所に収容された東條英機さんなどのA・B・C級戦犯の教誨(きょうか
い)をおこなった方です。
当時戦犯が収容されていた東京巣鴨の刑務所には、キリスト教の礼拝場が設けられ、専任の牧師もいました。
しかし、戦犯の収容者は90%以上が仏教徒です。これはやはり、仏教のお坊さんが必要だということで、当時東大の教授であり、本願寺派(西本願寺)の僧侶であった花山和上(わじょう)に白羽の矢が立ったわけです。
花山和上が巣鴨刑務所へいってみると、仏壇(ぶつだん)がありません。しらべてみると以前はここに仏壇があったのですが、それを豊(とよ)多摩(たま)の東京拘置所に移転してあることが分かりました。
「あなたは、あなたの本尊(ほんぞん)をもってきてよろしい」と、牧師から言われ、その移してあった仏壇と仏像を持ってきて、刑務所の中に仏間(ぶつま)を設けました。
そうしてこれから、この仏間で戦犯の方々とお経を上げ、み教えを語り合うのですが、和上はどうしても、ローソクと花とお香(線香)が欲しいと思われた。
その辺(あたり)の心境を「平和の発見」という著書に
戦犯者の「信仰」の友となるにあたって、何とかして、「仏間(ぶつま)」に出られる時だけでも、目と、耳と、鼻の三感覚を満たしてあげたいものだと、痛切に考えた。どうしても花と、ローソクと、そして香りのよい線香は、ぜひ欲し
かった。
活きた社会から全く隔絶され、冷たく凍っているこの人達の心へ、生き生きとしたもの、動くもの、明るいものを、投げ込みたいと念じたのである。
花と、ローソクと、線香は、どうしても欲しかった。しかし、当時焼跡の東京では、花の一束は、五十円出しても、なかなか入手が困難であった。人々は、食物(たべもの)におわれて、花をみる余裕など、まだ全然とり戻していな
かった。
と述懐されています。
どうしても欲しかった。
そこでわれわれの手では入らないが、米軍なら、何とかなるのではないかと、チャプレンのスコット氏に頼みます。
一旦は、「OK」を出してくれましたが、手続きをとってみるとやはり困難であったようです。
「ドクター花山、花はどうしても必要なのか。キリスト教では、なくても、式をすますことができるのだが」
再度、どうしても必要なのかと聞かれます。
「どうしても必要なのだ。これは、宗教的な立場から必要なので、テーブルにおく花として必要なのとは、全く意味がちがうのです」
と和上はこたえます。
「そうか、それなら、いったい何故宗教的に必要なのか、理由を説明してくれんか」
そう言われて、和上は思いつくままに、つぎのようにこたえられた。
「ローソクは、いわばライト、人生の光だ。これは、われわれの方からいえば、仏さまの智慧(ちえ)を象徴することになるのだ」
「そうか判った。では花はどうか」
「それはマースイ、慈悲(じひ)をあらわすものだ、ゴッドス・ラブ、神の愛を象徴する」
「うん、判った。では、線香は」
「それは、人間の罪を洗い清めるものなので、清浄を象徴する」
「それならよく判った。では何とかして花を世話してあげよう」
ということで、手配をしてもらって、そして、ローソクと花と線香を供えて、仏壇(ぶつだん)を荘厳(しょうごん)して教誨(きょうかい)をされたそうです。
仏さまのお徳を二つに分けると智慧と慈悲になります。
ローソクの炎は、闇を照らす光であり、心に暖かさと勇気を与えてくれるから、仏さまの智慧に象徴されるのでしょう。
花は、心を癒(いや)し、優しい気持ちを呼び起こしてくれるから、仏さまの慈悲に象徴されるのでしょう。
そして、仏さまの智慧と慈悲のはたらきが私に至り届いた姿を、お香によってあらわしているように思います。お香は、人間の罪を洗い清め、清浄をあらわすものとされています。
つまり、この三つをもって、仏さまの智慧・慈悲円満のはたらきが、この私に至り届いている姿を、私たちの感覚に分かるように、より具体的に表現したものかと思います。
仏さまを安置して、いろいろ飾ったり、お供えすることをお荘厳するといいますが、私たちの仏壇の荘厳は、仏さまのお国である浄土の荘厳を象(かたど)って(真似(まね)て)おこなっているものです。
浄土の荘厳一つ一つには、如来の功徳がそなえられています。
ですから、ローソクと花とお香で荘厳する私たちは、ただ単にものを飾るということだけではなくて、より身近な私たちの感覚に添って、導いてくださるための如来さま功徳が供わった、具体的な働きと受け取ることが大切なよう
に思います。
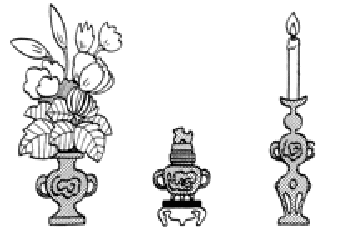
いのちは誰れのものか
ある中年の男性と、人間死んだらどうなるんだろうか、という話になったことがあります。
A 「ごんげ(権現)はん、人間死んだらおしまいでないけ。何も無くなってしもちゃ。みんなそう思うとっがいね。そやさかい、元気な間に楽しまんなんちゃ」
B 「そういう気持ちも分からんことないけど、死んだら何も無くなるというのちゃ。ちょっと言い過ぎでないけ」
A 「そんながなら何けごんげはん、死んだら霊魂でも残るちゅがけ」
B 「霊魂なんかにならんちゃ。念仏に生きるも者(もん)は仏様にならしてもらがやさかいに……。
そんな話じゃなくてね。大体、命(いのち)ちゃ自分のものでないねか、自分の思い通りにならんのやさかい。思い通りにならんもんは自分のもんでなかろがいね。」
A 「なら、誰のもんながね」
B 「仏さんのもんや」
「……………………………」
うまくその意味を伝えきれず、話はそこで止まってしまいました。
大抵の人は、自分の命は自分のものだと思っています。一面ではその通りです。しかし、また一面では、自分の命でないことも事実です。葬儀におまいりするたびに、いつもそのことを思い知らされます。
私でしたら、寺の息子に生まれようと思ったのでもないのに生まれてきてしまった。人間は生まれる環境を自分では選べません。せっかく生まれてきたのだから、いつまでも、若くて健康で長生きしたいと思っても、病気になり年をとって、自分の意思とは関係なく、やがて、或いは突然に死なねばならない命を生きています。あるいは、心臓ひとつ自分の意志で動かしているわけではありません。
自分の命でないからです。
大自然の恵み、いろんなはたらきや支えの中で生かされているのであって、自分一人では生きられません。
ですから、自分のものと思っている命と自分のものでない何か(命)を同時に生きているというのが事実ではないでしょうか。
二つのいのち
仏教で命については、概略このように教えていると思います。
命には、目に見える(形ある)命と目に見えない(形なき)命がある。形ある物質的命を支えているのは、目に見えない命であって、目に見えない命こそ、いのちの根源であり大地の世界である。その大地の世界では、それこそ宇宙が一つであるような、つながりとひろがりをもった永遠の命であり、我々はそういう形なき命の世界から、形ある物質的命に生まれてきて、そしてまた形なき命の世界に帰って行く。
その命の根源の世界を釈尊は、「縁起(えんぎ)」とか「真如(しんにょ)」「一如(いちにょ)」という言葉で表現してくださいました。
また、こんな説き方もされています。例えば地面に一輪の花が咲いている。ひまわりにしましょう。我々は地面から生えている部分だけを、ひまわりだ、ひまわりの命だと思いがちです。ところが、ひまわりは、大地に根をはり、水を補給しなければ、倒れてしまいます。つまり、大地とひとつの命を生きている。雨が降らなければ、二酸化炭素が無ければ生きられない。地球とひとつにつながっています。また、太陽が無ければ、光合成もできないから、宇宙ともひとつにつながっている。
一面では、地面から上だけがひまわりの命といえますが、同時にその根源は宇宙がひとつであるような命を生きてい
る。そういう二つの命を同時に生きているということがあるわけです。人間にも同じことが当てはまります。
共命鳥(ぐみょうちょう)
仏様のお国であるお浄土には、妙なる鳥がたくさんいて、その中に共命鳥という鳥がいると阿弥陀経に書かれています。
どういう鳥かというと、体が一つで、頭と心は二つあるという奇妙な鳥です。しかも、顔つきは人間に似ているようです。頭が二つ、心が二つという鳥だから、考えることも、食べ物の好みも違う。おまけに体が一つしかないのでうまく空を飛ぶことができません。飛ぶ方向が同じときはまだよいのですが、右と左に分かれて飛びたいと思うと、もういけません。バランスが崩れて、落ちてしまうのです。
ある時、それぞれの言い争いが起きました。
「おれはいつも、うまい物を食べ、平和に暮らしたいと思っている」
「偉そうなことを言うな。お前はいつだってうまい物を食ってるくせに、この おれには一度たりともくれたことがないじゃないか」
「お前が、おれに逆らってばかりいるからだ。おれが右へ行こうと言っているのに、お前は左へ行くと言って譲らない。平和に仲良く暮らそうと言っても、お前はちっとも言うことを聞かないではないか。ひねくれているお前がいけないのだ」
すると、ひねくれていると言われたほうはカッと頭にきた。
「自分一人がいい子になって、おれをばかにしてやがる。いまいましいやつめ、お前なんか殺してやる」
そう思った方の頭は、もう一方の頭に毒草を食べさせました。
興奮して体が一つしかないということを忘れしまったのでしょう。哀れなことに、身に毒が回って二羽とも死んでしまった。
そのようなことが雑宝蔵経に書かれています。
このお話は、命ということについて大切なことを私たちに教えてくれています。
それは、私たちは、お互いバラバラに自分一人だけの命を生きているように思いがちですが、命の本体では、ひとつにつながっている命を生きているということです。
分かりやすくするために単位を小さくして、家族ということで考えてみるとどうでしょう。
表面上は、身体も別ですし、バラバラに生きているようにも見えます。しかし、目には見えないけれど命の根っ子では、家族みんなが一つであるような命を生きているわけです。互いに支え合い、家族それぞれの苦楽が自分の苦楽であるような、そういう生き様。自分の生きるよろこびや使命も命の根っ子である家族はみんなが一つであるという精神からくみとっていることも多いのではないでしょうか。
この命の根っ子では、家族は一つにつながっているということは、割合気づきやすいことです。それが、無限のつながりとひろがりを持っている。生きとし生けるものはみんな命の根っ子では一つにつながっている。そう気づいた方を仏というのでしょう。だから、阿弥陀仏は、十方衆生すべての人が救わなければ、私は仏とならないとおっしゃった。
目には見えないが、命の根源では、すべての人が一つにつながっており、すべての人が救われるようにと願うことが、私の願いや使命の本源である。そのことを知らせてくける働きが、念仏という言葉となって私に届けられているわけです。
念仏申すということは、私の命の全体像を見つめ直し、命の根源から、私の生きる意味と使命を問い聞いていく営みであるともいえます。

葬儀のゆくえ
近年、葬儀のあり方が大きく変容してきています。家族葬、直葬(ちょくそう)(葬儀をしない火葬のみ)という言葉が違和感なく定着し、葬儀の小規模簡略化・多様化が顕著になってきました。病院で亡くなると直接葬儀社へ移送し、家は普段の様相と全く変わらず新聞の死亡欄にも掲載しない。隣の家の人が亡くなったことすら近所の人が全く知らいなという状況も、時折目にするようになりました。
平成二八年の公正取引委員会全国調査では、一般葬六三%、家族葬二八・四%、直葬五・五%、一日葬二・八%、社葬〇・三%となっています。平成二五年の関東圏でのNHK調査では、二二%が直葬であると報告されています。
今後ますます、家族葬、直葬は増え続け、僧侶を呼ばない葬儀、自由な形での葬儀など多様化が進んでいくことは、避けられない流れとなっています。
これらの現象をどのように受け止めたらよいのでしょうか。
そもそも歴史的に葬儀というのは、その時代その時代の社会状況や意識の現れであり、変化していくものである。ですから、今日の変化は、家族(並びに個人)と社会との関係性の変化が投影されたものであると言われています。
一昔前までは,三世代同居の大家族・親戚関係・地域共同体のつながりを大切にし、相互扶助の中で生活していたように思います。誰かが亡くなると、親戚や村中の人が総出になって、いろいろな役割や金銭(香典)を分担し、物心両面にわたって遺族を支援しました。各村に火葬場があったころは、その火葬の役も近所の人が分担したと聞いています。そうやって多くの人が悲嘆を共にし、つながりを深め、その大切さを確認していく場が葬儀でもあったように思います。ある意味で公な行事でした。
ところが、戦後は戦前の国家主義や全体主義への反省もあって、人類の普遍的な理念である、個人の自由と平等・人権を尊重する憲法のもとに歩みがはじまりました。別な言葉で言うと個人を尊重する「個人化社会」をめざすということなのでしょう。
「個人化とは、職業やライフスタイルや人間関係や消費などのあらゆることが、社会の規範や規則といった枠組みによらずに。個人の選択の対象になったきたことを意味する」と解説されています。つまり、伝統的な習慣やしきたり、世間体、周りが当たり前のように行っていることでも、それをどうするかは個人の選択の自由(自己決定)である。その個人の選択は尊重されるべきで、結果のリスクは自己責任として負うていくことが、めざすべき自律した人間像ということなのです。
戦後の産業構造の変化や少子高齢化・核家族化は、個人化を促進し、バラバラとなった個人が漂流する時代を迎えようとしています。
一九八六(昭和六一)年と、二〇一七(平成二九)年を比較してみると、三世代同居の世帯は一五・三%から五・八%に、夫婦と子供のみの世帯(核家族)は、四一・四%から二九・五%に減少しています。その一方で単独世帯は、一八・二%から二七%に、夫婦のみの世帯は、一四・四%から二四%に増大しています。
二〇四〇年には、単身世帯が全体の四割、六五歳以上の男性二割、女性の二・五割が一人暮らし、生涯未婚率は三割と予想されています。
このような個人化の傾向は、社会通念規範などから個人を解放する一方で、地縁・血縁・宗教縁の関係性が軽視され、人間関係を希薄にし、小さくなった家族と孤立化した個々人を生み出しました。それに併せて、葬儀の小規模化簡略化が目に付くようになってきています。葬儀は社会的な相互扶助の行事から、私的な家族内行事となり、葬祭業者にすべてを任せて、お金のかかる経済行為に成りました。沢山の人が金銭(香典)を負担してくれるわけでもありませんので、小規模化せざるを得ない面があります。法事などの死者追悼儀礼も簡略化されていく。
更には、家を継承する者もいなくなっていくということから、遺骨を継承する必要のない、永代供養墓、合同墓、樹木葬、散骨などの需要も増えてきました。
このような状況は、葬儀をはじめ。法事などの死者追悼儀礼を通して、聞法への機縁を深め、門信徒との関係を繋いできた仏教各寺院にとって、その存立基盤を根底から問い直さなければならない事態に直面させられています。
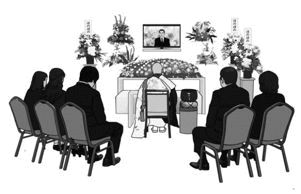
世界の幸福国
さて、この個人化は日本に限られたことではなくて世界全体がそちらの方に向かっているように思います。二〇一二年、実に国民の九七%が幸せだと意識調査で答えている、幸せの国ブータンが
国連を動かし、三月十四日を世界幸福デーに制定しました。ブータンのように経済優先ではなくて、国民一人一人を幸福にする施策を考えようということです。以来、毎年のように世界幸福度ランキングが発表されています。今年は世界一五六カ国中、一位からフィンランド、デンマーク、ノルウェー、日本は五八位、ブータンは九五位などとなっています。今までの調査では常に北欧が上位を占めています。社会福祉や保証がしっかりしているからなのでしょうか。北欧は全般にそうなのですが、特に今年の上位三か国は、すでに四割超が単身世帯です。つまり、一人で何不自由なく暮らせるのが幸せだということなのでしょうか。それが世界がめざすべき幸福の姿なのだ。個人化社会は、現代文明が生み出した必然的な方向なのかもしれません。
ですから、個人化は、嘆くことでも否定すべきことでもありません。だだ問題なのは、人間を支える共同性が弱体化し、それに伴って人間関係が希薄になってきたことです。
釈尊が気づいた命の事実
私の命は、私が作ったものではありません。いろんなものが、仮に依り集まって私を成り立たせています。そして、一人で存在している者は誰もいません。いろんな物や人とのつながりのなかで生かされ支えられてきた命です。生きる喜びも感動も苦難を乗り越えていく力も、そのつながりの中からたまわってき命です。そう気づいたら、つながっている相手の事を自分ことのように大切に生きていく慈悲の心こそ、私の命に宿った願いであると釈尊は教えてくださいました。
個人化の傾向は、あらゆる束縛から解放されて、人は一人になって自由なのかもしれません。しかし大切な命の事実を見失いがちになるような気がいたします。
今後、どんな葬儀や死者追悼儀礼の形式になろうとも、そのことを通して、自らの「いのち」の本質に目覚め、確認していくいとなみでありたいと思います。
悲しみと向き合う
人生において、近しい人を亡くすことはつらく悲しいことです。このような人に、釈尊はどのような説法をされたのでしょうか。二つ話を紹介したいと思います。
キサーゴータミー
キサーゴータミーという母親がいました。ようやくよちよち歩きができるようになったかわいい盛りの息子が、突然亡くなってしまったのである。彼女は悲しみに打ちひしがれ、気も狂わんばかりに泣き叫んだ。そして、親族の制止も聞かず、子どもを抱えたまま町のなかへ飛び出していきました。
「この子供を生き返らせる薬はありませんか。ご存知の方はありませんか」
町中を冷たくなった息子を抱えながら、うろうろと訪ねまわっています。
それを見かねた人が、お釈迦さまならその薬を知っていると、声をかけました。
それを聞いて訪ねに来た彼女に、釈尊は
「そうです。確かに、私はその薬を知っています」
「白いケシの実をひとつまみもらってきてください」
「それなら、私にもできそうです」
「ただし、キサーゴータミーよ。今まで死者を出したことのない家から貰ってきてください。死者を出したことのない家からですよ」
「はい、わかりました。お釈迦さま」
そういって、町に戻って一軒一軒訪ね歩きました。ところが、町中のどの家を尋ねても死者を出したことの無い家はありませんでした。
「ああ、なんと恐ろしいことか」
今まで自分の子だけが死んだと思っていたが、町中を歩いてみると生きている者よりも死者の方がずっと多い。死はどの家にもあると気づかされてきました。
夕刻になり、少し冷静になったゴータミーは、森に入り子供を手厚く葬ってから釈尊のもとへ再び訪ねます。
「どうでしたか、白いケシの実は手に入りましたか」
「いいえ、ダメでした。お釈迦さま、生きている者よりはるかに死人の方が多いことがわかりました」
「そうです。生きている者は必ず死にます。これは永遠に変わることのない法則である。(そのことを見ようとせず)家族への妄愛や財産へのとらわれに執着している人を、死王は苦しみの底へとさらっていくのである」と釈尊はさとされます。
そうして、ゴータミーは釈尊の弟子となり、自らの執着から解放された不死のやすらぎの境地をひらいた、と伝えられています。(ダンマパダアッカタ―
八・一三〈要約〉)
ウッビリー 尼
ウッビリーという母親がいました。ジーヴァーという娘を亡くし、我が子の名を呼び、泣き叫んでいます。そこを通りかかったお釈迦さまが、
「あなたは、ジーヴァー、ジーヴァ―と言って号泣しているが、どのジーヴァ―を悼むのか。この火葬場では八万四千人のジーヴァーという娘が焼かれたのである」
その時、彼女はハッと気がつきます。
「あなたは、私の心臓に突き刺さっていた見難い矢を抜いてくださいました。悲しみの妄執に打ち負かされていた私のために、その悲しみを取り除いてくださいました。お釈迦さま(仏)と、真理の教え(法)と、修行者の集い(僧)に帰依します」といって、仏弟子(尼僧)となっていきます。(テーリーガーター
第五二偈〈要約〉)
いのちの事実への気づき
このように釈尊は、悲しみに嘆く人に、自らのいのちの事実(無常)に徹底的に気づかせることによって、悲苦からの解放を説かれていきました。
この「いのちの事実」ということについて、修行道地経にヒントになるような話が書かれています。
子どもたちが、川辺の砂浜で城やら、家やら、動物やら、いろんなものを作って楽しそうに遊んでいました。すると、一人の子供が砂の城を壊してしまいました。作った子供は、「俺の城が……。俺の城が……。何てことしてくれる」と泣き叫びます。周りの子供も壊した子を責め立てます。壊した子供は「ゴメン、ゴメン」と泣きながら復元しようとしますがうまくいきません。
そんなことをしているうちにやがて夕暮れになって、みんな忘れたかのように家へ帰っていきます。残された砂の造形物は、波に流されて元の砂浜に戻っていきました。
というような話です。
これは私たちの命というものをあらわしているように思います。この話のように子供が作ったというならまだしもですが、私たちの場合は、一方的に与えられた命です。私が作ったものでもありませんし、私のものでもありません。それこそ宇宙が一つであるような、無限大のような砂浜の中で、いろんなものが仮に集まって、ある時は人間、豚、花などと形作られてきます。単なる砂の造形物にしかすぎません。作られたものが生滅変化を繰り返すのは不変の道理(無常)です。
人間の場合は、途中からこれは私の命で私のものであるという、自我の幻想が生まれます。そこで自分の思い通りにしたいという我執煩悩に縛られる。ですが、私の与えられているいのちの事実は、違う法則で動いています。自分の思い通りにはなりませんから、思い通りにならないことが、苦しみや悲しみとなって現れてきます。
実は、この苦しみや悲しみには重大な意味とメッセージが込められていると釈尊は気づきました。本来の私のいのちの事実から、我執煩悩に縛られている幻想を私だと思っているが、本当の自分はいのちの事実のなかにある。それに気づけというメッセージです。
宇宙が一つであるような砂浜で、人間という形になったり、豚になったり、花になったり……。人間として生まれても、若い時や健康の時もありますが、年老いて、病気になって、死んでいきます。これらの形の変化は、砂の造形物の変化であって、どれが良いとか悪いとかはありません。どのような形であろうと百点満点です。しかし、このいのちを我執煩悩でしか見れない私は、この形は良くて、この形は悪い。こんな形は幸福で、こんな形になったら不幸のどん底、苦しくて悲しいと執着しています。
その執着から解放されると、わたしのいのちの事実のなかに本当の私があるというのです。
いのちというのは、相互に依存し相互に支え合い、関係し合いながら一つのいのちを生きています。宇宙が一つであるような砂浜のいのちです。そのことを仏教では「如(にょ)(一つ)」という言葉で表現しています。親鸞様は『一切の有情はみなもつて世々生々の父母・兄弟なり』(歎異抄第五条)と云われています。みんな砂浜のようにどこかでつながっている親兄弟のような関係であるのだから、すべての人を自分のことのように大事に生きよう。相手の幸せが自分の幸せになる。慈悲に生きよう。その慈悲の心こそ私のいのちの事実に宿った願いである。そのことに気づけと釈尊は教えてくださったように思います。
ところが、頭のなかでは何となく理解できても、全く自我煩悩から解放されることの無い私がいます。その私のために「如(にょ)」から、形となり御名となって導き救うはたらきとして現れてくださった方が阿弥陀如来でありました。
  
|